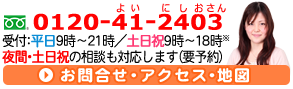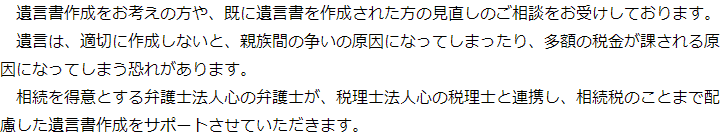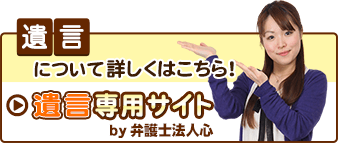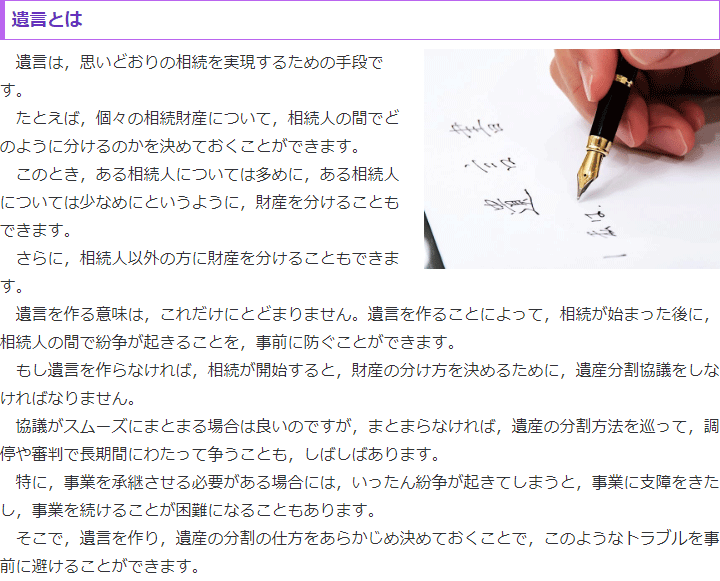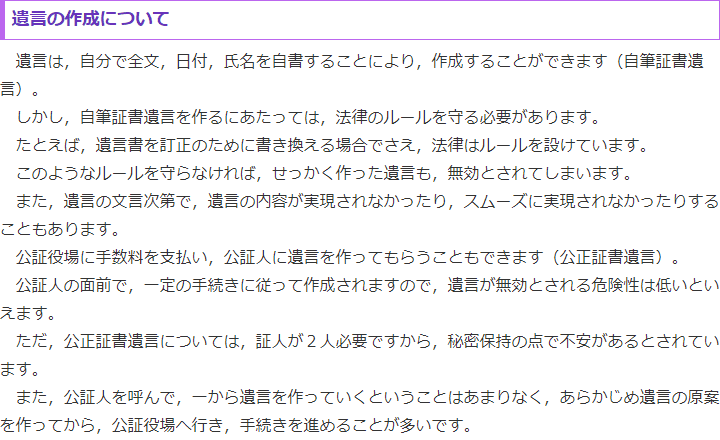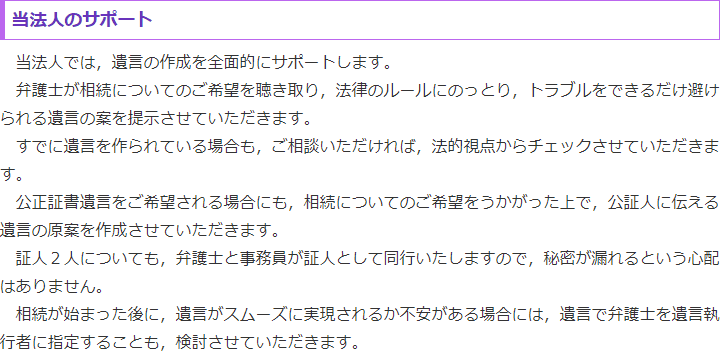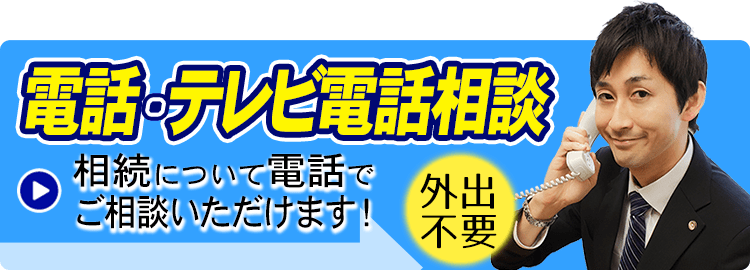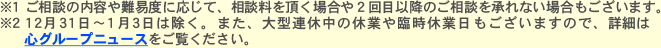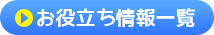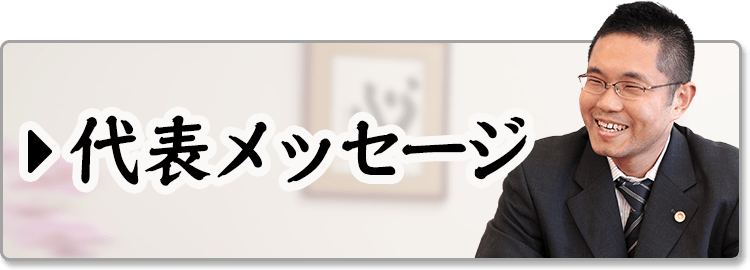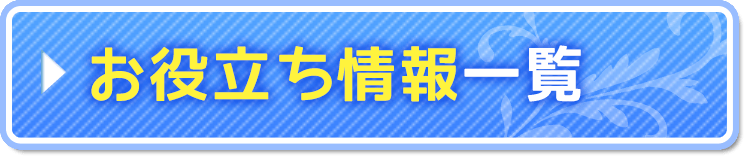遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言
1 自筆証書遺言

一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。
自筆証書遺言の要件は、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆することであり、さらに④押印することが求められます(民法第968条第1項)。
ただし、遺産目録を遺言書に添付する場合には、その遺産目録については自筆することは必要ありません(民法第968条第2項)。
自筆証書遺言は、上記要件を充たせば、遺言者が単独で作成できますので、費用もかからず、他人に知られることなく遺言書を作成することができます。
しかし、その反面、専門家によるサポートなく単独で遺言書を作成することで、遺言書の内容や有効性をめぐって相続発生後に相続人間でトラブルになる可能性があります。
また、自筆証書遺言が発見された場合、検認という手続を行う必要があります。
「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言を発見した場合、発見者は家庭裁判所へ検認の申し立てを行わなければなりません。
自筆証書遺言の場合、相続発生後に検認手続をしなくてはならず、手間がかかるというのもデメリットの1つといえます。
2 公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
その後、遺言者と証人が、公証人が作成した筆記が正確なことを承認し、各自遺言書に署名および捺印をします。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、正本が遺言者に交付されます。
公正証書遺言の場合には、公証役場が関与することで遺言内容の正確性や有効性が担保されるので、自筆遺言と比較する相続発生後に相続人間でのトラブルを防止しやすいといえるでしょう。
公正証書遺言の作成の流れ
1 自筆証書遺言と公正証書遺言

一般的によく利用される遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺言書のことを指します。
自筆証書遺言が有効に成立するためには、①遺言の内容となる全文、②日付、③氏名の全てを自筆し、さらに④押印することが求められます。自筆証書遺言は、公正証書遺言と比較して手軽に作成できる反面、紛失してしまったり、改ざんされてしまったりするリスクもあり、相続発生後に遺言の有効性が争われるケースも少なくありません。
これに対して、公正証書遺言とは、公証役場の関与の下、遺言者が遺言を作成するものです。
公正証書遺言の場合、遺言書の作成にあたっては、公証人と証人2名が関与します。
公証役場において、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容を筆記したうえで、遺言者と証人にその内容を読み聞かせ、又は閲覧させます。
公証役場で作成するため、自筆証書遺言と比較して作成の手続が煩雑ですが、遺言の有効性等で争いになるリスクを低くすることができます。
2 公正証書遺言作成に必要な資料
公正証書遺言を作成する場合、遺言書案のほかに必要な資料を公証役場に提出する必要があります。
まず、遺産の内容となる預貯金の通帳の写しや不動産の謄本、固定資産税評価証明書の写しが必要となります。
また、遺言者と相続人との関係を把握するため、被相続人と相続人の戸籍謄本の写しも必要となります。
遺贈をする場合には、受贈者の住民票の写しも必要となります。
さらに、公正証書遺言には実印で捺印することになりますので、公正証書遺言作成当日は実印を持参する必要があるほか、当該実印の印鑑証明書も用意する必要があります。
この印鑑証明書は、遺言作成日から遡って3カ月以内という有効期限があるので、注意が必要です。
公正証書遺言を作成する場合、上記のような書類が必要となりますし、作成の段取りもやや煩雑となります。
また、公正証書遺言の場合も、遺言書の記載をどのようにするべきか法的な検討が必要になります。
公正証書遺言を作成される場合には、弁護士等の専門家に一度相談することをおすすめします。
遺言を作成するタイミング
1 遺言はなるべく早く作成することがポイント!

遺言は早めに作っておくことが重要です。
遺言を作成するタイミングを後ろ倒しにすることで、作成できなくなるリスクが高まることがあります。
なぜかといえば、遺言を作成するためには、「遺言能力」が必要となります。
具体的に言えば、自分の財産等を誰にどう渡すかという遺言の内容を具体的に決定し、その法律効果について理解することができる能力のことを言います。
民法では、具体的には満15歳を遺言を作ることができる年齢と定めています(民法961条)。
この遺言能力を失うような事態が生じてしまうと、遺言を作ることが困難になってしまいます。
そして、そのような事態は、誰にでも、いつでも起こりえます。
「自分はまだ元気だから大丈夫」「重い病気になってから考えよう」というのは、遺言が作成できなくなってしまうリスクがあります。
そのため、なるべく、「まだ元気」な間に遺言を作成してしまうことが大切です。
2 遺言作成を後ろ倒しにするリスクの例
⑴ 作成する前に事故、病気によって死亡してしまった
遺言作成を後ろ倒しにしていた結果、事故に遭ったり、急な病気となって死亡してしまうという可能性があります。
これは決して珍しいことではなく、令和5年の高齢者以外の交通事故死亡者は1200人を超えています。
参考リンク:内閣府・令和5年中の道路交通事故の状況
このような不測の事態に備えておくことが遺言を作っておくこと利点でもあります。
⑵ 認知症等が発症してしまった
1のとおり、遺言を作成するには、ある程度の判断能力が必要です。
しかしながら、認知症になってしまうと、この判断能力が失われてしまうこともあり、遺言を作れなくなってしまうことがあります。
認知症ではなくとも、事故で死亡まで行かずとも植物状態となってしまったり、病気によって同じく判断能力が失われてしまうという事態も考えられます。
3 遺言を早めに作ることへの不安について
早めに作ってしまうと、自分が亡くなるまでに財産状況等が変化するなどしてしまい、有効な遺言にならないのではないかと不安を覚える方もいらっしゃいます。
この点は遺言の内容を工夫することで対処することが可能です。
例えば、あえて、金額など具体的数字は書かずに、特定できる最低限度の情報を記載して、細かな変化にも対応できる内容にするなどです。
もちろん、適切な内容でないと、遺言の有効性に問題が生じる場合はありますが、専門家に相談しながら作成すれば、そのリスクを減らすことは可能です。
また、遺言を、人生における重要な出来事毎に都度作り直す、ということも1つの選択肢です。
例えば、
独身の内は、自分の親に財産を遺す遺言書を作成する。
結婚したら、配偶者に遺す遺言書を作成する。
子供が生まれたら、子供にも遺す遺言書を作成する。
配偶者が亡くなったら、相続する相手から配偶者を除く内容で遺言書を作成する。
子供と不仲になったら、その子には財産を遺さない内容の遺言書を作成する。
孫が生まれたら、孫にも遺す内容の遺言書を作成する。
といったイメージです。
遺言は自筆で作成するのであれば、基本的に、いつでもどこでも作成することが可能ですので、何度も作ったとしても、それほど大きな負担にはならないこともありますので、こうした遺言のありかたも1つの方法であると思われます。
4 遺言の相談は専門家へ
ここまでの説明のとおり、遺言はなるべく早めに作ることが推奨されますが、同時に重要な書面でもありますので、適当に作ることは不適切です。
遺言を作成する目的に合わせて、内容だけでなく、複数ある遺言の形式から作成方法も選ぶ必要がある場合もあります。
また、遺言を作り直すことができるとはいっても、最初の1通については、記載内容等が分からないという方もいらっしゃると思います。
そこで、遺言書を作成する場合は、その内容や形式を含めて専門家に相談することが大切です。